飛行機って、いつでも自由に空を飛び回っているように見えますよね。
でも実は、飛び方にもちゃんとルールがあるんです。
このルールは天気によって変わることもあって、
「晴れの日」と「曇りや雨の日」では飛び方そのものが変わることもあります。
たとえば、空がよく見える日にはパイロットが目で周囲を見ながら飛ぶ。
でも、雲に囲まれて外が見えないときには、計器や通信を使って飛ぶ。
そんなふうに、状況によって“飛び方のスタイル”を変えているのが飛行機なんです。
この記事では、その2つのルールを、専門用語少なめでやさしく解説していきます。
空の飛び方にちょっと詳しくなれる、そんなきっかけになればうれしいです。
👀 晴れた日は「目で見て飛ぶ」スタイル
飛行機が飛ぶとき、外の景色がよく見えていれば、パイロットは“外を目で見ながら”飛ぶことができます。
これを「有視界飛行方式(Visual Flight Rules)」といいます。
その名のとおり、目に見える景色を頼りに飛行する方法です。
たとえば…
- 前方に他の飛行機がいないか確認する
- 地上の景色(道路や川、山など)を目印にしながら進む
- 雲や悪天候を避けながら、安全な経路を選んで飛ぶ
このように、自分の“目”が最大の情報源になります。
イメージとしては、晴れた日にドライブするような感覚。
ナビに頼らず、周りの景色を見ながら進む感じに近いです。
ただし、他の航空機とぶつからないように避ける責任(見張りの義務)は、すべてパイロットにあります。
だから、有視界飛行方式で飛ぶときは、周囲に注意を払いながら、状況に応じた判断が求められるんです。
🌧 曇りの日は「計器と指示に従って飛ぶ」スタイル
天気が悪くて外の景色がよく見えないとき、
たとえば雲の中を飛ぶような状況では、パイロットは“目”ではなく、計器や通信を頼りに飛行します。
これが「計器飛行方式(Instrument Flight Rules)」と呼ばれる飛び方です。
有視界飛行方式との大きな違いは、
目で見て安全を確保するのではなく、ルールと管制官の指示によって飛ぶこと。
たとえば…
- 雲の中でも、機体の姿勢や進行方向を計器で確認できる
- どこに他の飛行機がいるか、管制官が教えてくれる
- 地上が見えなくても、決められたルートを正確に飛ぶ
つまり、自分の「見える範囲」に頼らなくても、安全に飛行できるしくみが整っているんです。
イメージとしては、霧の中でナビと無線を頼りに運転するような感じ。
パイロット自身は景色が見えなくても、
機体に搭載された計器と、地上の管制官のサポートによって、正確に目的地までたどり着くことができます。
ちなみに、旅客機(エアライン)のほとんどは、天気に関係なくこの飛び方を使っています。
なぜなら、雲の中や夜間を飛ぶのはもちろん、空港周辺が混雑していることも多いため、
最初から計器と管制官による正確な運航が求められているからです。
✈️ 2つの飛び方の違いを表で比べる
| 比較項目 | 有視界飛行方式(VFR) | 計器飛行方式(IFR) |
|---|---|---|
| 目に見える景色 | よく見えることが前提(晴れているなど) | 見えなくてもOK(雲の中でも飛行可能) |
| 飛行の頼り方 | 目で周囲を見て安全を確保 | 計器と管制官の指示に従って飛行 |
| 天気の条件 | 比較的良好な気象が必要(視程・雲の高さなど) | 厳しい天気でも飛行可能(最低条件あり) |
| 他の機体との位置確認 | パイロット自身が目で見て避ける | 管制官が位置を把握し、安全間隔を指示 |
| 飛行の自由度 | 比較的自由(ルート変更も柔軟) | 原則として決められたルートを飛ぶ |
| よく使われる場面 | 小型機・訓練飛行・遊覧飛行など | エアライン・悪天候時の飛行など |
※この表では、初心者でも直感的に理解できるように、厳密な定義や例外を少し省いています。
📝 おわりに
空を飛ぶとき、パイロットは天気や状況に応じて「飛び方のルール」を使い分けている――
そんなお話をしてきました。
- よく晴れた日には、目で周囲を確認しながら飛ぶ「有視界飛行方式」
- 雲の中や天気が悪いときには、計器や管制の指示に従って飛ぶ「計器飛行方式」
飛行機は、「見えるから飛べる」だけじゃなく、
「見えなくても安全に飛べる仕組み」があるからこそ、世界中を飛び回ることができるんですね。
普段はあまり意識することのない空のルールですが、
今回の記事をきっかけに「飛行機って、こんなふうに飛んでるんだ!」と思ってもらえたらうれしいです。
この2つの飛び方は、実際のパイロット訓練にも深く関わっています。
次回の記事では、訓練中の視点から見た有視界飛行方式と計器飛行方式の違いについて、もう少し踏み込んでお話しする予定です✈️
そちらもぜひチェックしてみてください!


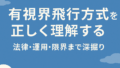
コメント